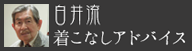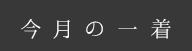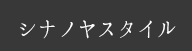うんちく | |
 エドワード黒太子のセーム革ガーントレット(1330〜1376年)  シアーズ・ローバックのカタログ(1897年)  スリッポン型長手袋(1930年代)  鹿革の礼装用手袋(1970年代 DENTS)  ライニング付ペッカリー手袋(1980年代 Fownes) |
グラブズ (Gloves 手袋)手袋の歴史手袋の最古(遺物)は、1920年代にエジプトの「王家の谷」から発掘されたツタンカーメン王の綴織りの手袋と云われています。 それは古代エジプト18王朝末のもので、素材には亜麻が使われています。 元来、手袋は手を保護することが目的で男性はスポーツ用が起源とされ、古代エジプトの婦人達は、食事の時にヤケドや手の汚れから護る為にも用いていたようです。 中世になると上流階級のスポーツとして鷹狩りが行われるようになり、今日のミトンに似た手袋で、鷹をのせる為の皮製が登場します。 また騎士や僧侶の叙位の役割や、市民権保持者への特権の印として象徴的な役割も果たしています。 その後11世紀まで手袋についての記録がほとんど見られず、17世紀になると華やかな最盛期に入り、18世紀に廃れはじめます。 男性用は形も簡単なものになりますが、婦人は社交用に欠かせないものとして重要しされます。 19世紀は丈も色々と変化し、シアーズ・ローバック社の1897年版カタログには数多くの手袋が掲載され、特に仔山羊革、豚革、それに鹿革の手袋が目立っています。 カタログのコピーとして「最低価格はオイルなめしの労働用手袋から、最高級は輸入の仔山羊手袋まで、すべて揃えています。」と表現されていたほどです。 20世紀は工業化の発展により、素材・デザインに富んだ手袋が広い階層に普及していきます。 その中で1920年代は鹿革や豚革が一般化し、1930年代中期には、手袋の色が男性の靴と帽子の色調から強い影響を受けるようになります。 その結果、黒と濃い茶色が手袋の基本色として確立されます。 また昼間の礼装用では生成り色が、夜には白無地でシャモア革(※)の手袋が主流となります。 現在では殆んど使用されませんが、当時は礼装の必需品で当店でも1970年代頃までは、取り扱っていたものです。 (※)シャモア革 羊やラム皮を魚油や海洋動物の油でなめした革。 日本においての手袋の変遷日本では鎌倉時代に鎧の篭手(こて)として発達したもので、当時は手覆(ておおい)とも呼ばれています。 西洋式の手袋は15〜16世紀頃の南蛮貿易によって輸入され、やがて国内生産も始まりますが、手袋作りは貧乏武士の内職として盛んになっていったようです。 また元禄時代(1700年頃)に赤穂浪士の大石主税が使っていた革手袋が残っているそうですが、今わかっているところでは、現存する中で一番古いものとされています。 現在、国内生産の約9割が香川県の東かがわ市で生産され、その歴史は1888年(明治21年)にメリヤス手袋の製造が始まりです。 その後、第1次世界大戦の特需や昭和20〜30年代の高度経済成長の波に乗り、アメリカを抜いて世界一になっていきます。
参考文献 |
|
Tweet
バックナンバー>> |
|